1. 関税交渉の概要と影響
2025年、米国との関税交渉が日本、韓国、EUの三者間で決着し、自動車に対する関税率が大幅に変更されました。
| 国・地域 | 交渉前の関税率 | 交渉後の関税率 | 増加幅 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 実質0%(FTA) | 15% | +15% |
| 日本 | 2.5% | 15% | +12.5% |
| EU | 2.5% | 15% | +12.5% |
韓国はFTA(米韓自由貿易協定)によって関税ゼロを享受していましたが、今回の変更で最も大きな打撃を受けることが予想されます。ただし、日本車・EU車も同様に高関税下での競争を強いられることから、各社は米国内での現地生産を加速させる方針です。
2. 現地生産化による輸送需要の減衰
2023年~2024年の米国向け新車輸出台数:
韓国:輸出台数の約47%が米国向け
日本:輸出台数の約25~32%が米国向け
極東(日本+韓国)から米国への輸出台数は約270万台、EUからは約112万台。合計約400万台が米国向けであり、これは自動車船による国際輸送の約18%に相当します。
この輸出台数が急激に米国内生産台数に切り替わることは想定されないものの、段階的な減衰は避けられないと見られます。
3. 自動車船輸送の将来予測
仮に、この輸送需要が15%以上減少した場合、以下のような影響が予想されます:
大型自動車船(6,000~8,000台積み)は寄港地数を増やす必要があり、運航効率の著しい低下が避けられない、中型船(4,000台以下)への切り替えが現実的な選択肢となりますが、現存する中型船は約160隻と大型自動車船に代わって輸送の主流になり得ません。
さらに中型船の船齢別内訳は下記の通りであり、全体的に老齢化しています。
10歳以下:75隻
11~20歳:60隻
20歳以上:25隻
一方で、2025~2026年には新造大型自動車船が150隻以上も就航する予定になっています。
このアンバランスにより、船社は採算の合わない大型船の運航を強いられ、一方では本来、運航効率が良く、かつ償却が済んだ低コストな中型船をスクラップせざる得ない可能性も否定できません。
4. 自動車輸送業界の岐路:バブルの終焉、再編の始まりか
コロナ禍以後、世界的な消費の爆発的拡大、そしてパナマ・スエズ両運河の通航制限で輸送距離が延びたことで、自動車船の供給不足が続き業界は空前の好景気に沸きましたが、現地生産化が進むことで輸送需要は年々確実に減衰します。さらに消費が沈静化し両運河の通航制限が緩和されれば、減衰スピードは早まります。これまでの歴史を見ると、輸送供給過多の場合、老齢船をスクラップすることで供給量を減らしていたようですが、今回は大型船の殆どが若齢なため財務的にも政治的にもそのような方策は取りづらいと思います。なお、大型船を保有していない会社には一定の勝機が見込まれますが、先述の通り彼らが現在保有している中型船は老齢化しています。自動車輸送業界が衰退するなかで、果たして新造船の発注に踏み切れるのか、今後の経営判断が問われます。
5. 将来性のある自動車輸送とは
世界の殆どの国々の自動車需要は、現地生産化に見合うほど大きなものではないため、今後もそのような国々と生産国との間の自動車輸送需要は存在します。しかし、輸出台数が少なく一航海当たりの船積み台数も少ないので、自動車船は複数の荷揚げ地に寄港する運航形態になります。経済効率の観点から大型自動車船が複数の荷揚げ地に寄港することは難しいので、大型自動車船は生産国からハブ港までまとめて輸送し、そこから中型以下の自動車船でフィーダー輸送を行うとか、あるいは、最初から中型自動車船で荷揚げ地を絞って輸送するなどの二通りの運航形態をめざすことになるでしょう。
生産国から遠距離にある消費国への輸送は、投入船舶の選定、ハブ港の選定・整備、フィーダー船の手配などの長期戦略に基づいた大がかりな仕組みが必要になるため、先ずは、生産国から近距離にある複数の消費国への輸送を確保することが重要です。近距離輸送は一般的に遠距離より運賃が低いですが、中型以下の少数の船でサービス維持が可能なので設備投資を抑えることがでます。さらに運航の工夫次第で稼働日数(貨物を輸送している日数)の向上も可能であり、利益率を上げるのは比較的容易です。今後は、いち早く近距離、多頻度輸送を確立した会社に将来性があると考えられます。
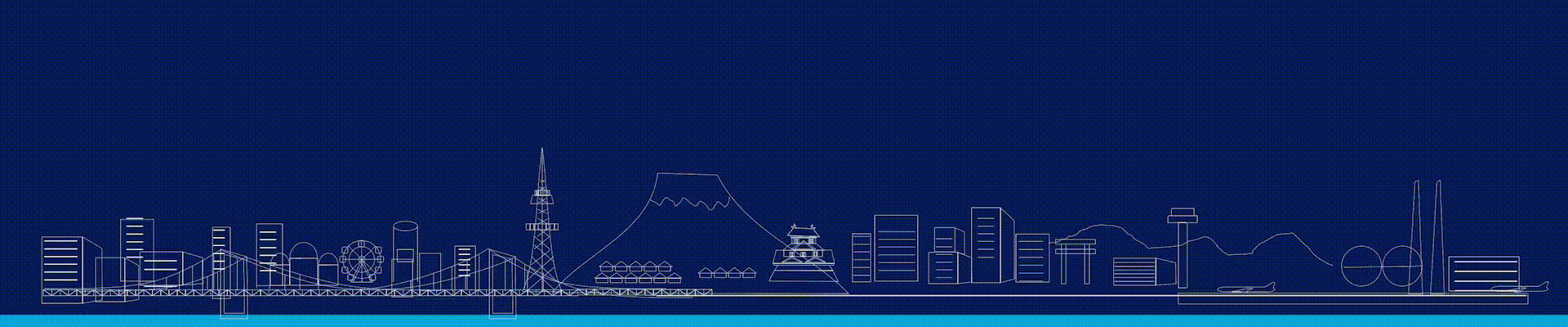
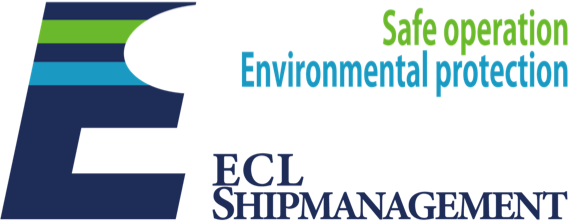
Login to comment